
お び
飫肥城

| 所在地 | 宮崎県日南市飫肥 |
| 形式 | 平山城 |
| 主な城主 | 伊東祐兵 |
| 遺構 | 曲輪・石垣・空堀・土塁 |
| 指定・選定 | 市指定史跡・日本100名城 |
| 訪城年月日 | 2025年3月20日 |
| 満足度 | A B C D E |
| 登城難易度 | A B C D E |
| 車での登城 | 不可 |

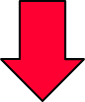
中央が初代藩主伊東祐兵の墓
神社奥にある伊東家累代墓地(拡大可)

五百禩神社説明版(拡大可)
城から南西600mほどの場所にある五百禩(いおし)神社
~江戸時代には伊東家の菩提寺・報恩寺が建っていたが、
明治に入って廃寺となり、五百禩神社が建立された~
伝・伊東祐兵着用鎧(歴史資料館内)
大手門
大手門(昭和53年再建)




旧本丸虎口
旧本丸虎口


旧本丸虎口




旧本丸説明版(拡大可)



本丸跡
~本丸跡には飫肥小学校が建っている~

松尾の丸下の石垣


本丸南側虎口


本丸石垣(櫓台?)
本丸石垣


本丸西側虎口(内側)


本丸西側虎口
大手門西側の土塁

大手門内側
~枡形構造となっている~
大手門枡形内






飫肥城は、中世には島津氏と伊東氏の抗争の舞台として、近世には飫肥藩伊東家の居城として、現在の宮崎県を代表する城であった。
酒谷川に囲まれた北側の一段高いシラス台地を縦横に空堀で区画した広大な城域を持ち、各曲輪の独立性の高さが特徴となっている。
江戸時代の前期に本丸と二の曲輪とされている範囲だけでも、東西約750メートル、南北500メートルに及ぶ広大な城であった。
飫肥城の大手門は明治6年(1873)に取り壊されたが、昭和53年(1978)、飫肥城復元事業の第二期工事として、当時城郭研究の第一
人者であった故藤岡通夫氏の設計・監修により、国内に現存する大手門を参考にして在来工法で再建された。再建された大手門は、木造
渡櫓二階建て、高さ12・3メートルを測る。建築材は、飫肥営林署(当時)の三ツ岩学術参考保護林(現在、三ツ岩オビスギ遺伝資源希少
個体群保護林)から樹齢百年の飫肥杉4本の提供を受けた。工事中に、礎石に刻まれた正徳3年(1713)銘の碑文が発見されており、
現在、大手門の内側に保存されている。
なお、現在みられる城内の石垣の大半は、貞享3年(1686)から元禄6年(1693)の大普請によって改修されたものである。
<現地案内板より>
飫肥城
城跡遠景と酒谷川
旧本丸北門(再建)
旧本丸
~江戸時代に3度の大地震に遭って地割れが発生したため、
元禄6年(1693)に現在の本丸跡に移転した~
旧本丸虎口(東口)
旧本丸切岸
旧本丸切岸
本丸跡にある飫肥城歴史資料館
本丸石垣
大手門枡形内
大手門
大手門手前の空堀
旧本丸土塁
本丸から旧本丸へ